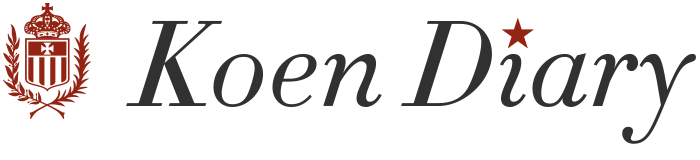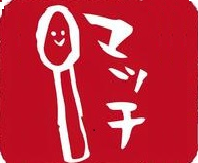
マッチ先生が贈る今月の一句ー12月 マッチ先生が贈る今月の一句ー12月
本広げこたつに入り居眠りす
読書には足熱厳禁睡魔用心
学校は冬休みに入り、今年も残すところわずかとなりました。
帰省する人、旅行する人、ショッピングに行く人など、冬休みの過ごし方は、さまざまだと思います。
この冬休みはどのように過ごそうと考えたとき、私はじっくり本を読んでみようかなと思いました。どちらかというと出歩くのが好きな人間ですが、最近、心のゆとりがなくて本を読まずに過ごしていたため、心がカサカサになってしまった感じがするので、このお休み中は家で読書の時間を取りたいと思ったのです。そのとき、ふと思い出したのは、『徒然草』第十三段の一文です。
「独りともし火のもとに文(ふみ)を広げて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよなう慰むわざなる。」
「文」というのは書物を指し、「見ぬ世の友」は知らない昔の人すなわち古典の作者や登場人物を指します。本を読むことは孤独な作業で、一方通行の感がありますが、実は作者や登場人物と対話しているのだと、兼好は言っているのではないでしょうか。読書によって、人とつながることができると言っている気がします。
光塩では、今年は「つながる」プロジェクトの一環として、地域社会との関わりや留学生の受け入れなど、人との関わりを強めてきました。現在この世に生きている人とのつながりが大事なのはもちろんですが、時代や空間を異にする人とつながることも大事だと思います。古典の読書を通じて、古人が生きた時代を知ることができ、与えてくれた教訓も受け取れるのだと思います。
この冬、古典を読んで古人とつながってみませんか。