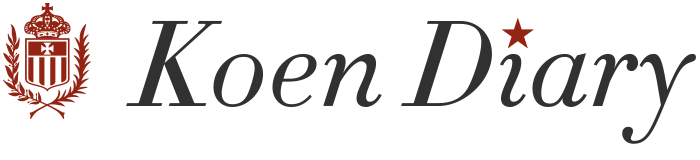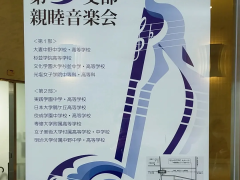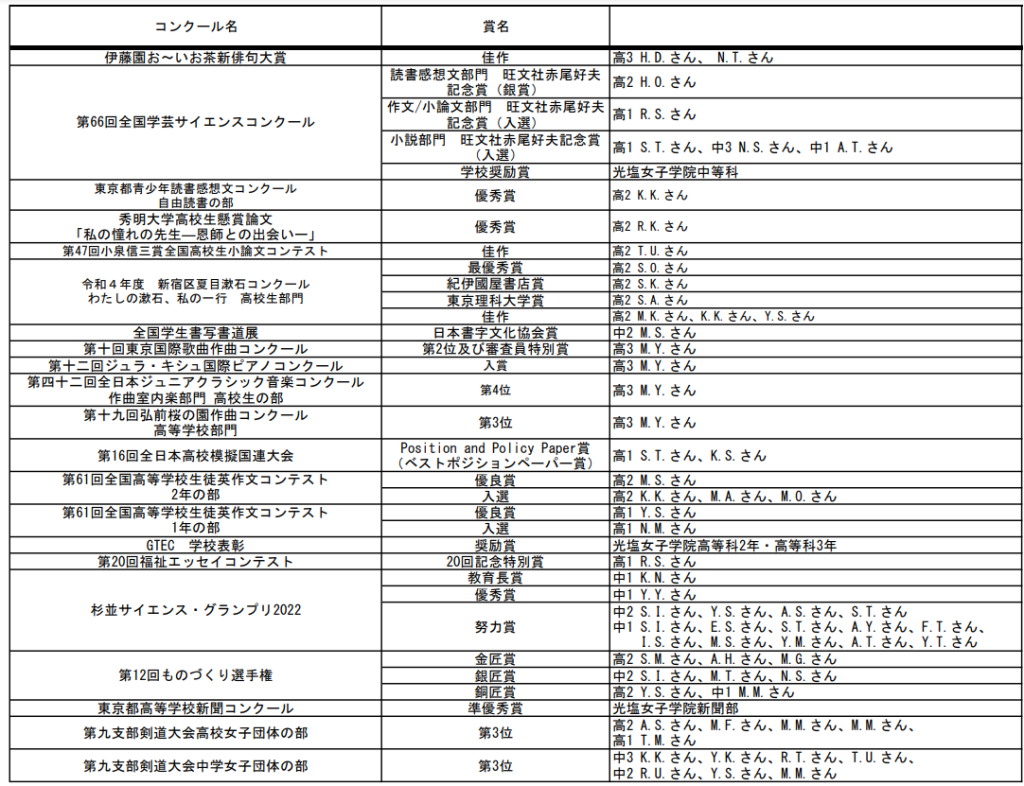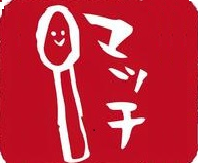
マッチ先生が贈る今月の一詩 マッチ先生が贈る今月の一詩
マッチ先生が贈る今月の一詩
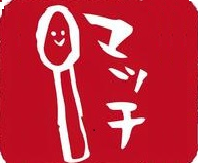 「ひらくということ」
「ひらくということ」
耳が開かれている時には、いろいろなもの音が聞こえる。
目が開かれている時には、いろいろな人やものが見える。
そして、心が開かれている時には、たくさんのことばが入ってくる。
本当に、これでもかこれでもかというぐらいおもしろいように。
「ひらく」ということは、とても勇気のいること。
なぜなら、ひらくことで出ていくものもあるから。
もしかしたら、出ていってほしくないものもあるかもしれない。
ひらくことで失うものもあるかもしれない。
ひらくことで傷つくこともあるかもしれない。
でもひらいてはじめて見えてくるものがある。
少しだけ勇気をもってひらいてみよう。
その時、きっと思いがけない風景が見えてくる。
それがあなたへの、神さまからのメッセージ。
寒さの中にも梅の花のほころびや日脚の伸びに、春の兆しを感じるように
なりました。1月は、年が新たになるとともに生きとし生けるすべてのも
のが新たに「ひらかれる」、そんな気がします。
そんなことを考えながら、今月は詩を作ってみました。自身に言い聞かせ
つつ、皆さんへのエールとしてこの詩を贈ります。