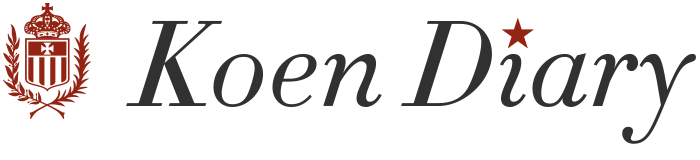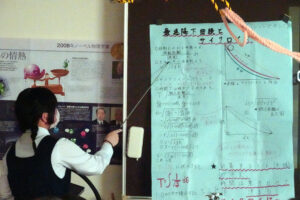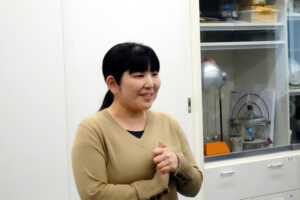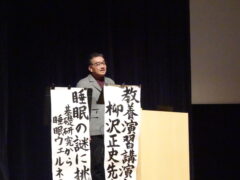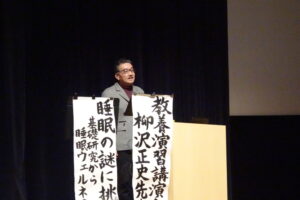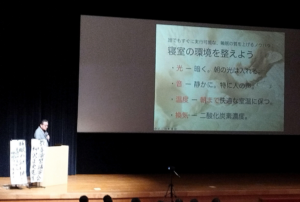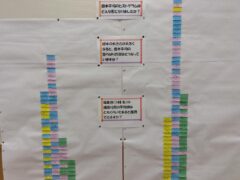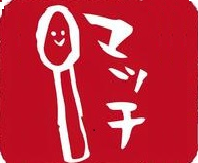
マッチ先生が贈る今月の一句ー3月 マッチ先生が贈る今月の一句ー3月
「さまざまの事思ひ出す桜かな」芭蕉
3月に入ってからも寒い日が続き、東京でも雪が降ることがありましたが、ようやく冬将軍から解放されそうですね。これまで寒かっただけに急に暖かくなって、桜が一気に咲く気配。本当の春はもうそこまで来ています。桜は蕾の状態ですが、梅は盛りを過ぎ、海棠はすでに咲き始めています。咲く時期は異なりますが、いずれもバラ科の植物です。桜はご存じのとおり、花見の定番として多くの人に愛でられますが、梅の上品な香もまた、古代から和歌に詠まれ、愛されてきました。海棠の華やかな様は楊貴妃になぞらえられ、もてはやされています。
このように植物たちは、同じ科であっても、それぞれの個性を持っており、優劣などつけられません。私たち人間も同じです。皆それぞれにかけがえのない存在なのです。
書家で詩人でもある相田みつをさんは、「自分が自分にならないでだれが自分になる」という言葉を書いていますが、本当にそのとおりだと思います。
4月から新しい世界に入っていく皆さん、ぜひ自分のまま、置かれた場所で花を咲かせてくださいね。応援しています。
最後に門出する皆さんに、駄句を一句
「旅立ちに幸あれと祈る親心」