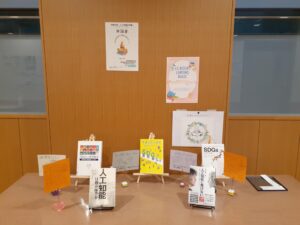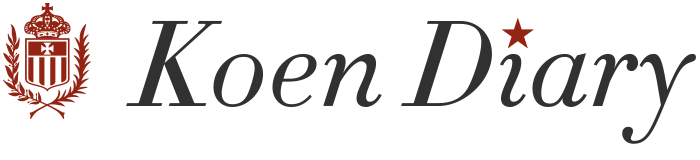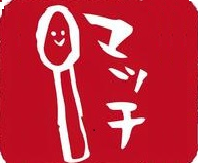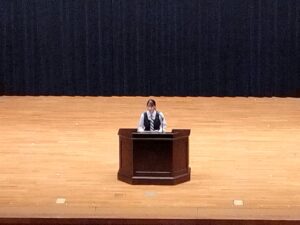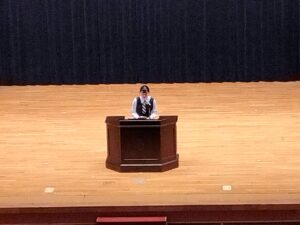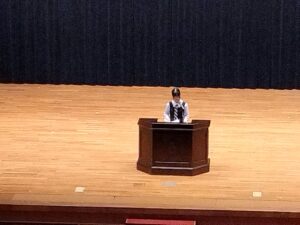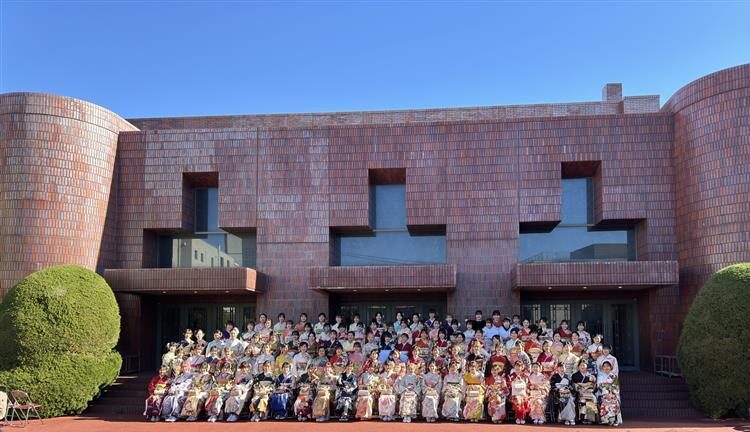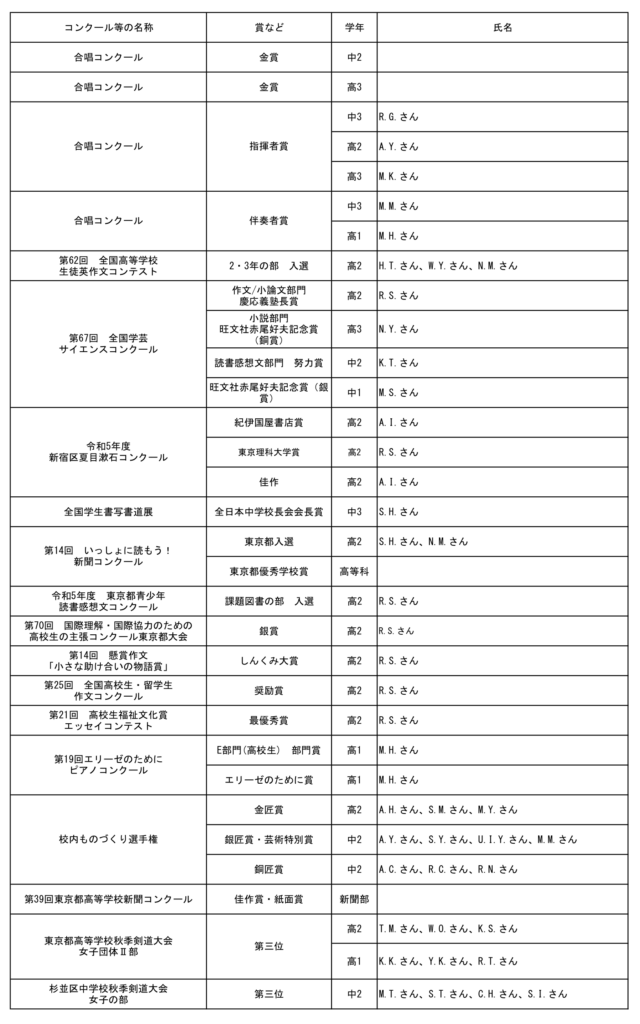山茶花(さざんか)のこぼれて季(とき)の往くを知る
日脚伸び川面(かわも)に遊ぶ小鴨たち
新しい年を迎えたと思っていたのに、気づくと1月も残りわずか。まもなく立春を迎えます。
受験生の皆さんは4月から始まる新しい生活に思いを馳せて、ラストスパートをかけていらっしゃることでしょう。受験学年ではない方も新年を迎えて心新たに次の学年への目標を定めていらっしゃるでしょう。中には、進路決定に思い悩んでいる方もいるかもしれませんね。
新年度に向けての準備が始まるこの時期に、皆さんにぜひともお伝えしておきたいことがあります。それは、どんな選択も自分で選び取ってほしいということです。小学生までは保護者の方の敷かれたレールの上を歩いてきた方がほとんどでしょう。でも、皆さんの人生は皆さん自身が歩んでいくもの。他の人が代わって歩むことはできません。自分の進む道は自分で決める—当たり前のようですが、意外と難しいことだと思います。しかし、自分で決めて自分で選び取らないと先々必ず後悔します。これは私自身の経験から言えることです。
「いのちを運ぶで運命、その運転手は自分」
「自分が育てて来た自分、自分が育てていく自分」
上の2つは、薬師寺の僧侶である大谷徹焋(おおたにてつじょう)さんの言葉です。自分でよく考えて選び取り、それで思い描いたとおりの結果にならなかったとしても、自分自身で歩みだした事実は残ります。それは大きな自信に繋がると思います。
自分を自分自身で育てていきましょう。自分の運命を自分の手で切り開いていきましょう。皆さんの明るい未来を信じて応援しています。