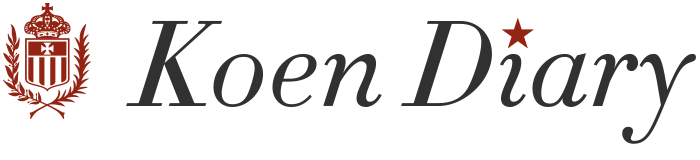高二 漱石文集 高二 漱石文集
高二文系の生徒は、文学国語Ⅰを履修します。半年かけて漱石の随筆『硝子戸の中(うち)』を読み、徹底的に考え、それを繰り返し表現していきます。学びと思索を通して一人ひとりが漱石の「不可知の深淵」に迫った経験を書き記したものは、「漱石文集」としてまとめられます。その内容の一部を紹介します。
・自身を、「今日も明日も死なずに生きている」事実を当然だと安直に受け取る人間の一人だと見なしながらも、運命や時の支配に翻弄される人間を俯瞰する姿勢は、余裕のある作家・漱石としての姿を如実に表しているといえるだろう。
・世界は多面的で、 私たちがどの側面に目を向けるかによって感じ方は変わる。 目を背けたくなるような一面がある一方で、美しい側面も沢山あるからこそ、 漱石が書くように人間の根本義は生の上にこそ存在するのであろう。
・生きるとは何か、悶々と考えていると視界はどんどんぼやけてくる。 何も分からなくなる。だがこのような読書体験が、 この世を分かった気にさせてくれる。 それが私を少し生きやすくする。 私は生きることで、私の思う美しい生き方を見つけていきたいと強く思う。
・漱石にとって「死」は理想であった。時の支配を受けず、虚偽やエゴイズムとは無縁の絶対の境地である死を、時に漱石は「人間として達し得る最上至高の状態」とさえ表した。しかし、その理想の境地に辿り着くことよりも、漱石は己の弱点を発揮しながら人間の現実である「生」を生きていくことを選んだ。
・ 『硝子戸の中』で、漱石は真実を見極める目をもって世の中を眺め、一方的な批判をせず、自分の原体験を振り返り、丁寧に言葉を紡いでいる。現代の大変多事な世の中で、寸暇を惜しむ私達は、効率の良さばかりを追求し、自分の中で考え言葉を紡ぐという作業を疎かにしがちである。しかし、紡がれた言葉はたとえ忘れられたとしても、本質は記憶の底に沈殿し、いつまでも心の中に残り続ける。この経験こそが現代の私たちにとって、本当に大切なことなのかもしれない。(続編に続きます)
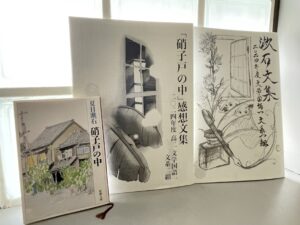
右の2冊が漱石文集。表紙も生徒の手になるもの。